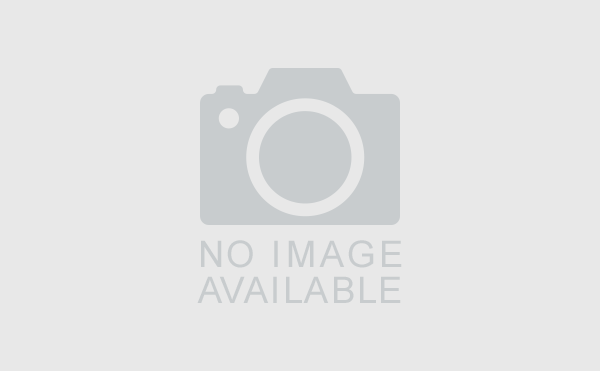同じ方向を向く組織をつくる、任せる文化と柔軟性の両立
1. はじめに
中小企業において、組織の一体感を持たせるためにMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)が整っているのが理想です。
しかし現実には、限られた経営資源の中で理念や行動指針の整備に手が回らない企業も少なくありません。
そんな環境下でも、組織をバラバラにせず、同じ方向を向かせるために重要なのが、任せる文化の育成です。
2. 中間管理職のジレンマ
組織には、経営者側と労働者側で価値観や考え方にズレが存在します。
経営者は経営目線で判断し、現場は現場目線で行動する。どちらも正しくても、視点の違いから摩擦が生まれます。
この板挟みに苦しむのが、中間管理職です。
上層部からの要求と、現場の現実。その狭間で揺れ動き、疲弊していく管理職は少なくありません。
このズレとジレンマを放置すれば、現場は混乱し、組織全体がバラバラに動き出してしまいます。
3. 任せる文化
そこで求められるのが、現場への権限移譲です。
ただし、それは単なる自由放任ではありません。
現場に一定の裁量を与えることで、中間管理職のジレンマを和らげ、意思疎通を滑らかにします。
さらに、状況に応じた迅速な対応が可能になり、組織が外部環境の変化にも柔軟に対応できる体質へと変わっていきます。
任せることは、バラバラになることではありません。
任せるからこそ、一つの方向へ進める組織をつくるのです。
4. 任せてもバラバラにならないために必要なもの
権限を与えるだけでは、組織はまとまりません。
現場が迷わず動き、連携して進めるためには、最低限の「土台」が必要です。
それが、方向づけと共通言語です。
これらは、正式な行動指針とは異なりますが、
現場判断を揃え、組織の一体感を保つための実践的な工夫です。
4-1. 方向づけ──判断に迷わない軸を示す
現場に裁量を与えるなら、「何を大事にするか」という基準は必ず共有しなければなりません。
たとえ理念が完璧でなくても、最低限の方向性は示すことができます。
たとえば、
- 「お客様との信頼を最優先にする」
- 「短期的な利益より、長期的な関係構築を重視する」
こうしたシンプルなメッセージでも、現場の迷いを減らし、判断に一貫性をもたらします。
4-2. 共通言語──現場をつなぐ“連携の合言葉”
さらに、現場同士がバラバラにならないためには、共通言語が重要です。
ルールやマニュアルではなく、日常的に使える「合言葉」が連携を支えます。
たとえば、
- 「迷ったら巻き込め」
- 「一人で抱え込まない」
こうした言葉が現場に浸透することで、孤立や誤解を防ぎ、権限移譲による動きを組織全体で支えることができるのです。
5. まとめ
任せる文化を育てることは、組織の柔軟性を高めるだけではありません。
組織をバラバラにしないための最も現実的な手段でもあります。
方向づけと共通言語を整え、現場に一定の裁量を持たせることで、
それぞれが自律的に動きながらも、全員が同じ方向を目指して進んでいく組織をつくる。
これが、限られた経営資源の中でも中小企業が生き残り、成長していくための現実的な組織論だと、私は考えます。
2025.4.27
甘夏ニキ