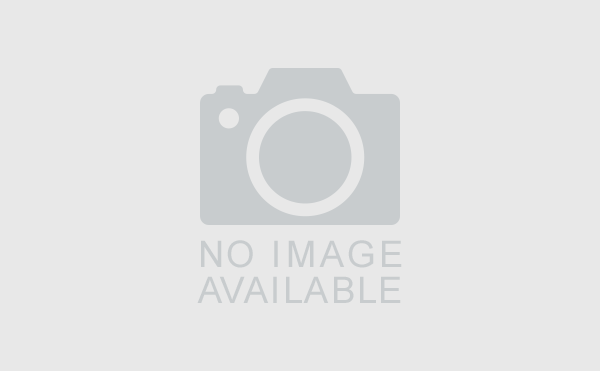減反政策が日本農業を歪ませた─米価、補助金、制度疲労の果てに
1. 税金で米を作らせないという“異常”
日本の農業政策における減反政策(生産調整)※1は、「米を作らない農家に補助金を出す」という逆転した仕組みで長年維持されてきました。これは一見、供給過剰を抑えて価格を安定させる“市場調整”のように見えますが、実態は税金で生産を止めて価格を吊り上げているに過ぎません。
その結果、国民は税金によって補助金を負担し、さらに高い米価を支払うという“二重の負担”を強いられているのです。
2. 減反が支えてきた“兼業農家”の現実
私の実家も兼業農家でした。だからこそ、減反政策の恩恵を実感として理解しています。米価が維持されることで、少ない収穫量でも一定の収入が確保でき、農業を続ける意味があったのです。
しかし、この恩恵は実は小規模農家や兼業農家にとってこそ大きかった。作付け量が少ないほど、市場価格が高ければ利益が出やすく、補助金と合わせて生活の支えになっていたのです。その一方で、この構造が農業の集約化・大規模化を妨げ、日本の農業を全体として非効率で低収益なまま停滞させてきたのもまた事実です。
3. 大規模化を阻み、改革を止める構造
減反政策は、単に米を作らせない政策ではありません。農協や地域の農業委員会が生産調整を“管理”することで、農地の流動化を阻み、農業経営の自由度を著しく制限してきました。
小規模農家が生き残り、大規模農業が育たない。これは単なる“意欲の差”ではなく、構造的に規模拡大が報われにくい制度のせいです。これでは農業が事業として成り立つはずがありません。
4. 誰も手をつけられない、政治と社会の壁
減反政策が温存されてきた理由は、農業界だけにあるわけではありません。JA(農協)、農水省、そして地方基盤を重視する自民党という三位一体の構造が長年、この仕組みを守ってきました。
しかしそれだけではありません。多くの国民もまた、「農家は守るべき存在」という漠然とした感情を持っています。農業を批判すること自体が“冷たい”と受け取られがちで、改革の議論が表に出にくいのです。制度疲労が進んでも、誰も声を上げず、変えられない状況が続いてきました。
5. 守るべきは制度ではなく人
だからと言って、小規模農家を切り捨ててよいとは思っていません。私自身、兼業農家の出身だからこそ、その痛みも恩恵も理解しています。ただし、構造としての減反政策をこのまま続けていけば、次に壊れるのは“農業”ではなく“日本社会”そのものです。
守るべきは制度ではなく人。だからこそ、構造を変えた上で、支援が必要な農家には個別保障や移行支援を手厚く行うべきです。農業が再び持続可能な産業としてよみがえるためには、「守る」と「変える」を両立する覚悟が求められていると、私は強く感じています。
※1「減反政策」とは正式には「米の生産調整政策」の通称で、1970年代から長らく用いられてきました。2018年には国主導の生産調整は廃止されましたが、補助金制度や地域による作付調整の実態は今も続いており、本稿ではその意味で「減反政策」と表現しています。
2025.5.11
甘夏ニキ