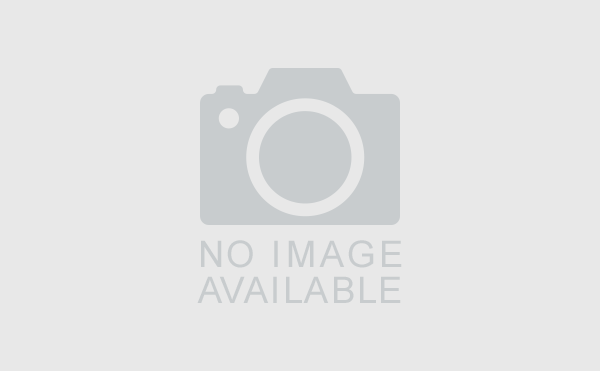人型ロボット市場の未来、日本の戦略と可能性
◆ 中国は人型ロボットで前のめり、日本はなぜ沈黙しているのか
現在、中国では人型ロボットの商業化が急速に進んでいます。傅利葉智能(Fourier Intelligence)、宇樹科技(Unitree Robotics)、智元機器人(Agibot)などの企業が次々に製品を発表し、量産化へ移行しています。ショッピングモールでの案内や倉庫業務など、用途を限定した導入も進んでおり、Teslaの「Optimus」も2025年の実用投入が視野に入っています。
一方、日本はASIMOやHRPシリーズなどの技術的な蓄積を持ちながらも、人型ロボットの商業展開では目立った動きを見せていません。政府や大手企業の姿勢も消極的です。
◆ 失策か、それとも戦略的な選択なのか
表面的には、日本はこの分野で遅れを取っているように見えます。しかし、視点を変えると、人型ロボットとしての完成品の主導ではなく、供給網や技術の支配に重点を置く戦略を選択している可能性があります。
日本は過去に家電市場を失い、現在の半導体戦略においても、ロジックICの開発よりも材料・装置・工程などの基盤技術の強化を優先しています。同様に、人型ロボット市場でも、いずれコモディティ化することを見越し、サプライチェーンの主導権を握る方向にシフトしているのではないかとの見方も考えられます。
◆ 人型ロボットのコモディティ化と日本の戦略
どれほど高度な技術を持つ製品であっても、量産化が進むと価格競争が激化し、差別化が困難になります。人型ロボットも例外ではなく、将来的には「どこでも作れる完成品」に近づく可能性があります。
この状況では、収益を得られるのは代替の効かない部品・プロセス・設計思想を持つ企業です。日本がこれらの分野で優位性を確保すれば、市場が成熟した段階で極めて重要な立場を占めることになります。
◆ ロボットの量産には高度な技術と現場力が不可欠
人型ロボットが社会に広く普及するためには、自動車産業と同様に、高度なすり合わせ技術とオペレーショナル・エクセレンスが求められます。関節の駆動系、姿勢制御のセンサー群、高出力バッテリー、リアルタイム制御技術の統合など、それぞれが独立した技術として成立するだけでなく、精密な調整を施しながら連携させる必要があります。
また、ロボットの量産が本格化すれば、効率的な生産体制の確立も不可欠です。これは日本が長年培ってきた「カイゼン(継続的改善)」の文化に根ざしたオペレーショナル・エクセレンスが大きな強みとなる部分です。日本企業は生産ラインの最適化において世界でも屈指のノウハウを持っており、人型ロボットの量産が進むほど、その技術力と現場力が生きてくるでしょう。
◆ サプライチェーン支配と完成品産業の両立
だからこそ、日本に必要なのは、供給網の強化と完成品産業の復活を両立する戦略です。静かに産業基盤を支えるだけではなく、政府の支援を受けて完成品市場にも再挑戦する必要があります。
人型ロボットは単なる技術革新ではなく、次世代産業構造の鍵となる存在です。部品、工程、設計、運用のすべてが揃ってこそ、人型ロボットは社会に広く普及します。この変革期において、日本がより積極的な主導権を握ることが求められています。
2025.4.26
甘夏ニキ