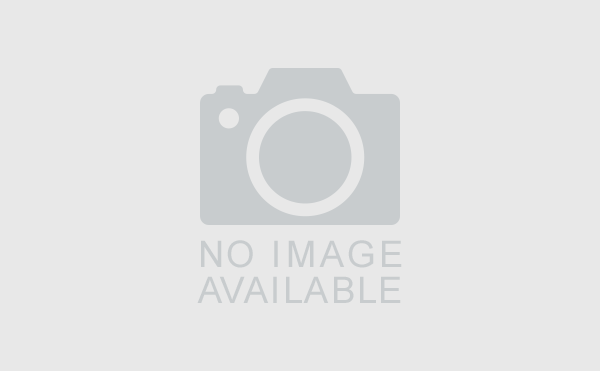積極財政と緊縮財政の狭間で――ソブリン・アクティビズムという第三の道
1. 積極財政と緊縮財政の狭間で
AIやロボットが人間の労働を代替し始めた今、「働いて稼ぐ」という当たり前の常識が崩れつつある未来に直面しています。工場の自動化だけでなく、ホワイトカラーの知的業務さえもAIによって再構築され、いずれ「働かなくても生産される」時代が本格的に到来する可能性があります。
このとき、社会にとって決定的に重要になる問いは次の通りです。
「誰が、どのように、所得を得て、消費を担うのか?」
少子高齢化は先進国が必ず直面する構造的な宿命ですが、それ以上にAI時代は「所得と労働の切り離し」という根源的な課題を突きつけています。この変化に単なる少子化対策や雇用対策では対応しきれません。
2. 第三の道を求めて
財政政策の議論は「積極財政」か「緊縮財政」かの二項対立に陥りがちです。前者は国債発行や財政出動を肯定し、後者は財政健全化を重視します。ベーシックインカム(BI)のような所得補償策も議論に上がりますが、「財源はどこか?」「税か?」という議論にとどまりがちです。
しかし、必要なのは「購買力の裏付けとしての税や借金」ではなく、「信認される通貨」という観点です。信頼される通貨こそが社会の購買力を支え、再分配の基盤となります。
3. ソブリン・アクティビズムの核心
私が提案する「ソブリン・アクティビズム(Sovereign Activism)」は、直訳すると「主権的能動性」と言い、これは国家が通貨主権を単に守るのではなく、戦略的・能動的に活用するという構想です。従来の財政政策では税収と国債発行が主な手段でしたが、ソブリン・アクティビズムでは通貨主権を積極的に活用することで、新しい経済運営モデルを構築していく事にあります。
例えば、日本が輸出やインバウンドによって外貨を獲得し、経常黒字、厳密には貿易収支を積み上げれば、円は国際的に買われ、円高圧力が高まります。これは円の信認が高まる状態です。こうした通貨であれば、政府が国債を発行しても金利は安定し、通貨価値も維持されやすくなります。
この仕組みを活用すれば、国家は税収に過度に頼ることなく、国債発行を通じて社会保障や将来投資の原資を確保できます。つまり、外需によって通貨の信認を得た上で、内需の購買力を支える。この構造こそが、次の時代に必要な経済の基盤になると考えています。
4. インフレと信認のバランス
このモデルで懸念されるのがインフレのリスクですが、外需主導で円高が進めば輸入品価格が抑制され、むしろデフレ圧力が働く可能性があります。さらに、通貨の信認が強固であれば、国債発行による通貨価値の下落や金利上昇も抑えられるため、インフレは一定の範囲内で制御可能です。
ただし、過剰な支出や供給能力を超えた需要が続けばインフレ圧力は避けられません。そのため、「信認の維持」と「支出の質のコントロール」が重要になります。信認を失えば、インフレと通貨安のリスクが急速に顕在化するため、外貨を稼ぎ、国際的に評価される国家戦略が必要になります。
5. 通貨主権を活かした未来への提言
社会にとって、「誰が稼ぎ、誰が支え、誰が消費するのか」という問いに真剣に向き合う時代が到来しています。AIやロボットの普及により、「働いて稼ぐ」という従来の枠組みが崩れる中で、所得の再分配は避けられないテーマです。
ここで重要なのは、税による再分配でもなく、単なる国債発行による財源確保でもない、信認された通貨による再分配という第3の経済運営モデルによる国家戦略です。
日本は「高い通貨信認」と「通貨発行権」を同時に持つ稀有な国です。だからこそ、円の信認を基盤とした分配モデル、すなわち「ソブリン・アクティビズム」は、日本の新たな成長戦略であり、社会保障のあり方そのものを進化させる鍵になると信じています。
2025.4.13
甘夏ニキ