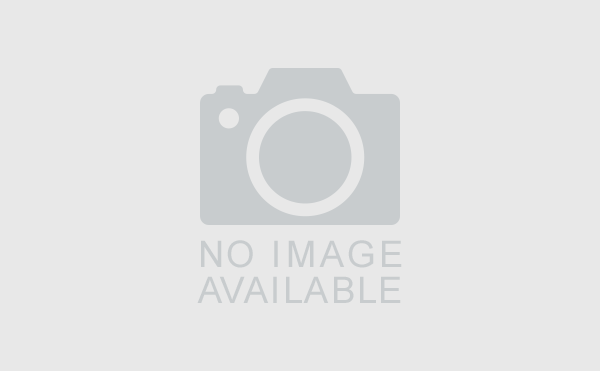「現場を知れば農業はできる」という幻想が農業を壊している
1. 農業研修制度が前提にしている“現場主義”の考え方
農業を始めるためには、各自治体や研修機関で1〜2年の研修を受けることが、新規就農者にとって事実上の前提となっています。その背景には、「農業は現場で学ばなければ身につかない」という考え方があります。作物の栽培方法を体で覚え、土壌や季節の変化を経験しながら学ぶ。こうした“職人的な農家像”に基づいた研修制度が、現在も広く採用されています。
しかし、現代の農業はこうした伝統的なアプローチだけでは成り立ちません。経営戦略や販路開拓といった視点がなければ、持続的な農業経営は難しいのが現実です。
2. なぜ制度が意欲ある人を遠ざけてしまうのか
1〜2年の研修期間は、多くの人にとって大きな負担となります。特に、すでに農業に関わっている人や副業・兼業として農業を始めたい人にとっては、この長期間の研修がハードルとなり、柔軟な学び方が選択できない現状があります。
また、研修を受けなければ農家と認められず、補助金の対象にもならないという制度の運用が、一部の意欲ある人材を遠ざけている側面があります。制度は本来、農業の発展を支えるものですが、画一的な研修を求めることで、農業経営の経験や知識を持つ人でも参入しにくい状況が生まれています。短期資格や実績を考慮した認定方法があれば、より多様な人材が農業に関われるはずです。
3. 「農業は簡単だ」という誤解が失敗を招く
もう一つの問題は、研修制度と補助金制度が結びつくことで「研修さえ受ければ農業ができる」「現場の経験があれば経営はなんとかなる」という安易なイメージを生んでしまっていることです。
しかし、実際の農業経営は、収益の管理、市場動向の把握、人材育成、資金繰りなど、多岐にわたる課題があります。農業を始めたものの、経営の厳しさを理解しきれず、数年以内に離農してしまうケースも少なくありません。「農業は簡単に始められる」という誤解が、かえって事業の失敗を招いているのです。
4. これからの農業に求められるものとは
農業の未来を築くには、現場での経験だけでなく、経営力・戦略・技術を含めた総合的な視点が必要です。制度は「現場作業者」を育てるだけではなく、「農業経営者」としての成長も支援できる仕組みへと転換していくべきです。
現場での経験を重視することは重要ですが、それだけを一律の条件として課すのではなく、多様な学び方や認定ルートが必要ではないでしょうか。農業を本気で志す人が、柔軟な制度のもとで知識や経験を積みながら発展できる仕組みこそ、今求められているのではないでしょうか。
2025.5.8
甘夏ニキ