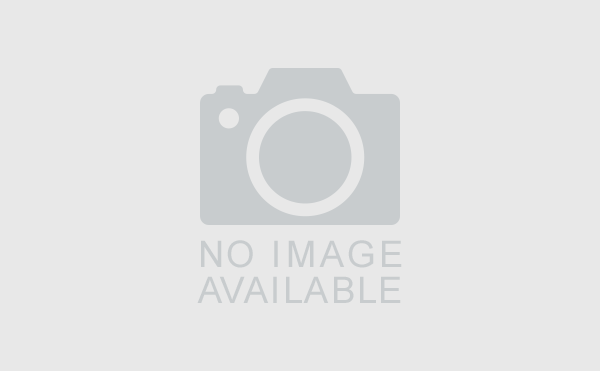AIとロボット開発最前線、進化したすり合わせの先にある“狭間の技術”とは?
◆ 1. 高度統合設計(進化したすり合わせ)とは何か
AIとロボティクスの融合が進む現在、ハードの設計思想である部品を現場で微調整して仕上げる「従来のすり合わせ技術」だけでは対応できなくなっています。現在のAIとロボットの統合開発モデルでは、仮想空間において目的を定義し、構造・制御・AIのアルゴリズムを統合設計する「高度統合設計力」が主流となっており、これは言わば「進化したすり合わせ」と呼ぶことができます。
この設計力により、目的(たとえば階段を登る)に応じて、AIが関節角度・歩幅・重心移動を学習し、仮想空間で得た動作モデルを現実世界に適用することが可能になります。ただし、摩擦・剛性・センサー誤差など、現実の物理的条件との“ズレ”が生じやすく、最終的な微調整は避けられません。
◆ 2. それを超える「狭間の技術」とは
この「高度統合設計」に対して、まったく新しいアプローチとして注目されるのが、古田貴之氏(千葉工業大学 未来ロボット技術研究センターfuRo 所長)のモデルに代表される「狭間の技術」です。
狭間の技術とは、AIと構造、仮想空間と現実環境、制御と感覚情報といった“異なるレイヤー同士”を、後から統合するのではなく、最初から「共に育てる」アプローチです。
設計思想が「動作を設計する」から「動作が発生する場を設計する」へとシフトし、AIが自身の身体構造を理解しながら、自律的に動作を創発するという点が決定的に異なります。
◆ 3. 比較シミュレーション、階段を登らせてみる
狭間の技術を分かり易く理解するためにシミュレーションで比較してみます。たとえば「階段を登る」という目的を設定した場合、高度統合設計(進化したすり合わせ)では以下のような流れになります。
- 目的を明示(階段を登る)
- 仮想空間で最適な動作(関節の動き、バランス)をAIが習得
- 現実世界で微調整(摩擦・硬さ・ズレ)
- 所要時間:短め
- 仮想→現実のギャップ:大きい
一方、狭間の技術では:
- 目的は明示しない(階段はあるが「登れ」と指示しない)
- ロボットは仮想空間で自身の身体構造を理解しながら、動作を自己発見
- 環境に対して最も自然な動きを創発し、結果的に階段を登る
- 現実のギャップ:極めて小さい
- 所要時間:長め
このように、時間はかかっても「狭間の技術」は、より自然で再現性の高い動作を実現します。
◆ 4. 日本の未来、狭間の技術を国家戦略へ
日本は、すり合わせ文化によって高度統合設計力(進化したすり合わせ)を支える素地があります。しかし、それを越えて「狭間の技術」へと進化できるかが、次世代の競争優位性を決定づける鍵です。
狭間の技術は、設計というよりも「共創」の領域です。そして、それはAI時代における日本の新しい設計思想になり得るものです。
これを国家戦略レベルで位置づけ、研究開発、産業応用、人材育成に組み込んでいくことが、日本が再び世界のロボット先進国として躍進するためのカギとなるでしょう。
2025.5.4
甘夏ニキ