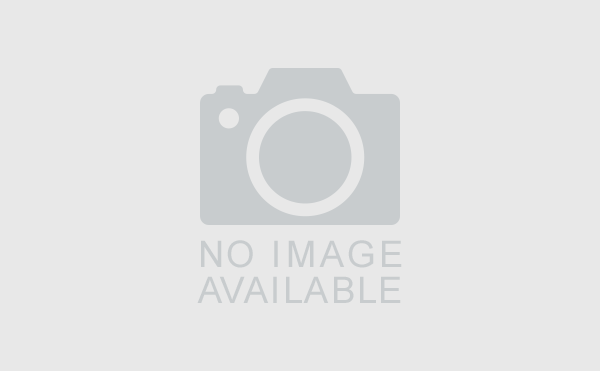人型ロボットと日本の勝機、いま問われる「進化したすり合わせ」
◆人型ロボットの時代が始まった
AIとロボティクスの融合により、人型ロボットの社会実装が現実味を帯びています。中国ではFourier IntelligenceやUnitree Roboticsが量産モデルを発表し、アメリカではTeslaのOptimusやFigure 01が商業化を前提に開発を進めています。仮想空間で学習したAIを搭載し、人間のように歩き、判断し、作業するロボットが登場するのは、もはや時間の問題です。
かつてロボット先進国だった日本は、現在どの位置にいるのでしょうか。ASIMOやHRPシリーズをいち早く開発したものの、近年の商業化競争ではその姿があまり見られません。
◆日本はまだ“出遅れた”わけではない
日本は人型ロボットに必要な要素技術において、世界トップクラスの実力を維持しています。高性能なモーターやセンサー、精密な減速機構といった部品は日本メーカーが信頼を得ており、部品の誤差を調整して完成させる「すり合わせ」の技術も日本の得意分野です。
この「すり合わせ」は単なる部品調整ではなく、設計・製造・品質管理を統合し、製品として成立させるプロセス全体を含みます。また、品質を維持しながら大量に供給するためのオペレーショナルエクセレンス(OE)も日本の強みです。つまり、日本は「素材・組立・量産」の三拍子を備え、人型ロボットの量産において有利な立場にあります。
◆しかし、それだけでは十分ではない
現在のロボット開発の革新は「AIとの統合」にあります。仮想空間でAIに動作や判断を学ばせ、現実のハードウェアに適用する手法が主流です。しかし、仮想空間で学習した動作も、摩擦や剛性、遅延といった物理的制約のある現実世界では、そのまま再現できません。この「ズレ」を吸収し、適応させる力が求められています。
◆そこで必要となる「進化したすり合わせ」
日本は、試作と改良を繰り返しながら精密に調整する「すり合わせ」に強みを持ってきました。しかし、現在必要なのは、AI・構造設計・制御アルゴリズム・実装環境を統合し、設計初期段階から整合させる「高度統合設計力」です。従来のすり合わせ技術をさらに発展させたものであり、私自身これを「進化したすり合わせ」と呼んでいます。
これは仮想空間でAIが学んだ動作を、現実世界に無理なく適用するための統合的な設計思想と技術の集合体だといえます。
◆日本の再浮上の突破口
日本のロボット産業が世界から遅れているとは限りません。むしろ、「進化したすり合わせ」の実装力において、製造業で培ってきた蓄積が強みになります。課題は、それを現代の文脈で再定義し、戦略的に実装できるかという点です。部品の優位性だけでなく、それらを「つなぐ力」を進化させることで、日本は再びロボット大国として世界の主導権を握る可能性を十分に持っています。
2025.5.3
甘夏ニキ