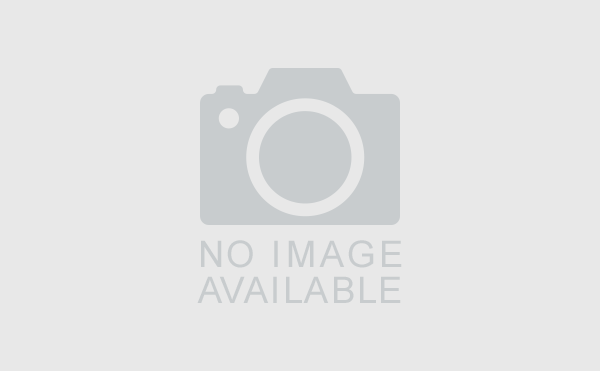BCPを“現場任せ”にしていませんか?詰むのは“データ”と“お金”です
◆BCP策定率15%の現実。でも“実は半分やれている”説
「うちはBCPなんてやってませんよ」中小企業の現場では、こんな声をよく聞きます。
実際、統計上もBCP(事業継続計画)をきちんと策定している中小企業は、全体の15%前後にとどまっています。
けれど、よくよく話を聞いてみると、「緊急時の安否確認はLINEグループで済ませてる」「部長が不在のときは、課長が代わりに指示する流れは決まっている」など、BCP的な要素はすでに現場の中に根付いていることが多いのです。
つまり、「BCPの文書はないけど、感覚的にBCPはやれている」というのが、日本の中小企業のリアルなのかもしれません。
◆BCPとは何か?
BCP(Business Continuity Plan=事業継続計画)とは、災害や事故、パンデミック、サイバー攻撃などの不測の事態が発生しても、事業を止めずに継続または早期再開するための計画です。
大企業ではマニュアルや訓練が整っていても、中小企業にとってはハードルが高く、「BCPは書類づくり」と誤解されているケースも少なくありません。
しかし本質は、“何があっても会社が倒れないようにする”ための、実務ベースの備えなのです。
◆本当に“詰む”のはどこか?BCPの盲点は2つある
とはいえ、「なんとかなる」では済まされない領域があるのも事実です。
それが、「情報システム」と「資金」の問題です。
仕入れ先や生産設備のトラブルなどは、ある程度現場の判断や時間の経過で回復できます。代替先の候補があったり、業務委託先に振り分けたり、機材が届けば生産再開も可能でしょう。
しかし…
データが消えた、会計ソフトが開かない、取引先の情報が全部飛んだ、という事態には、現場の“機転”は通用しません。
加えて、手元資金が底をつけば、復旧作業どころか人件費の支払いすらできず、企業としての継続が絶たれます。
◆なぜ“情報とキャッシュ”が即死リスクなのか?
情報システムのトラブルは、単なる業務停止にとどまりません。
顧客情報が消え、会計・販売ソフトが動かず、受発注データが失われる。これだけでも信用は一気に毀損されます。復旧に数日かかれば、取引停止や契約解除も起こり得ます。
一方、キャッシュが尽きると、それはもう“即死”に近い状態です。
生産が止まっても、ローンの返済は待ってくれません。
売上がゼロでも、社員の給料は支払わなければなりません。
さらに、もし災害によって重大な事故や死亡事故が発生すれば、莫大な損害賠償責任や訴訟リスクが降りかかります。
その時、保険に入っていなかった、キャッシュがなかった、という状態では、もはや事業どころの話ではなくなります。
情報と資金、この2つに共通するのは、
“一度失えば、取り返す時間も手段もない”という点です。
だからこそ、この2つはBCPの中でもっとも深く備えておくべき“即死リスク領域”なのです。
◆BCPを生きた戦略にするために
BCPは、分厚いファイルを作ることが目的ではありません。
「いざという時に、誰が・どこで・どう動くのか」が、実際に動く“仕組み”として実装されているかどうか。それこそが真価です。
特に、次のような致命的リスクに対して、具体的な備えがあるかどうかが問われます:
- データはクラウドにバックアップされているか?
- 火災・水害・労災・損害賠償への保険加入は万全か?
- 月商の3か月分程度のキャッシュを確保しているか?
- 緊急時にすぐ相談できる融資窓口や信用保証枠はあるか?
- 補助金申請の加点対象となる「事業継続力強化計画」の認定は取得しているか?
これらはすべて、“もしものとき”に会社が潰れないための最低限の防御策です。
BCPを“実働する戦略”に変えるとは、つまり、
「想定外を、想定内にしておくこと」。
どんなに現場が優秀でも、情報と資金が断たれた瞬間、企業は動けなくなります。
だからこそ、BCPを“指揮命令系統の構築”だけで済ませず、データとお金に対する備えも、ピシャッと整えておくことが中小企業の真のサバイバル戦略なのです。
2025.6.25
甘夏ニキ