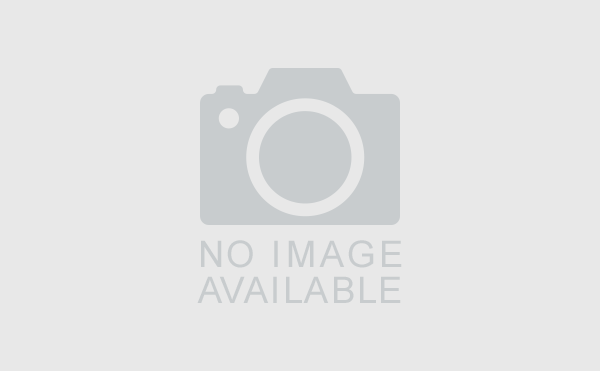雇用保険法改正がもたらす人材流出の危機と企業の対応策
令和6年に成立した「雇用保険法改正」は、多様な働き方を支えることを目的としています。この改正により、雇用保険の適用範囲が拡大され、教育訓練やリ・スキリング支援が充実し、育児休業給付に関する制度が見直されました。
しかし中小企業にとってこの法改正の意義を理解しておかないと思わぬリスクにさらされることになりかねません。特に令和7年4月1日施行の「自己都合退職者が教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除」は、労働市場に大きなインパクトを与えることが予想されます。
◆改正のポイント
①雇用保険の適用拡大
・被保険者の要件を週所定労働時間「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大します。これにより、より多くの労働者が雇用保険の対象となります。
【施行期日: 令和10年10月1日】
②教育訓練やリ・スキリング支援の充実
・教育訓練給付金の引き上げ…給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げ、訓練効果を高めるためのインセンティブを強化します。
【施行期日: 令和6年10月1日】
・自己都合退職者が教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除…失業給付の制限期間が2ヶ月から1ヵ月に短縮されます。また自己都合で退職した者が職業訓練を受けた場合、給付制限をせずに雇用保険の基本手当を受給できるようになります。これにより、再就職やスキルアップを支援します。
【施行期日: 令和7年4月1日】
・教育訓練支援給付金の給付率引下げ…基本手当の80%から60%に引き下げます。ただし暫定措置を2年間延長し、令和8年度末まで継続。この見直しにより教育訓練受講者への支援を2年間継続します。
【施行期日: 令和7年4月1日】
・教育訓練休暇給付金の創設…在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合、その期間中の生活を支えるために、基本手当に相当する新たな給付金が創設されます。
【施行期日: 令和7年10月1日】
③育児休業等給付の拡充
・出生後休業支援給付の創設…出生後8週間以内に父親が14日以上の育児休業を取得した場合、支給される給付金です。これにより、父親の育児参加を促進します。
【施行期日: 令和7年4月1日】
・育児時短就業給付の創設…育児のために短時間勤務を選択した場合、賃金の一部を補償する給付金です。これにより、育児と仕事を両立しやすくします。
【施行期日: 令和7年4月1日】
◆「自己都合退職者が教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除」とは?
令和7年4月1日より離職者に対して失業給付の制限期間が2ヶ月から1ヵ月に短縮されます。また、厚生労働省指定の約16,000の講座で教育訓練を受けた場合、給付制限をせずに雇用保険の基本手当を受給できるようになります。これにより、退職に対するハードルがかなり低くなるといえます。
◆まとめ
退職に対するハードルが低くなる点からわかる通り、この法改正のねらいは「雇用の流動化」です。雇用の流動化は労働市場が活性化することで企業の労働生産性を高め、最終的に賃上げの源泉となることを目指しています。企業は必要な人材をより容易に獲得し、業務効率が向上します。一方、働き手にとっても自分のスキルやキャリアに適した職場を見つけやすくなります。これにより、労働市場全体の柔軟性が増し、労働者と企業の双方にとって有益な環境が整います。
しかし、雇用の流動化は企業側にとって人材が離職しやすいという大きなリスクも伴います。このため、企業はしっかりとした人的投資を行い、労働者に対して魅力的な職場環境やキャリア成長の機会を提供することが重要です。
2025.3.9
甘夏ニキ