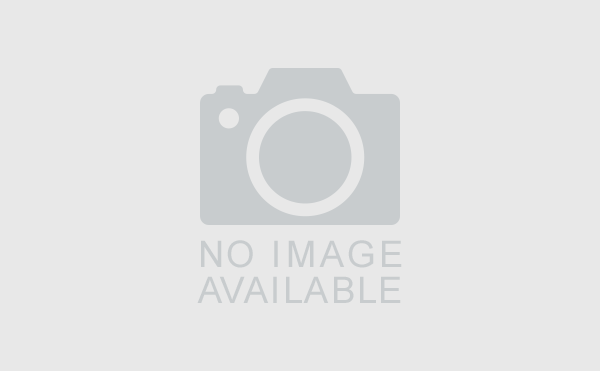日本の“解雇規制”は本当に厳しいのか?問題は制度より“雇用のかたち”にある
◆ 「日本は解雇が厳しい」は本当か?
「日本は解雇が厳しい国だ」とよく言われます。たしかに、アメリカのat-will employment(随意雇用)のように、雇用主が比較的自由に解雇できる制度と比べれば、日本の制度は慎重です。しかし、フランスやドイツなどのヨーロッパ諸国と比べれば、日本の解雇規制は中程度とも言われています。
つまり、日本の制度は世界的に見て特別に厳しいわけではありません。では、なぜ「解雇がしにくい」と感じられているのでしょうか。その背景には、雇用の文化や運用の仕方そのものが影響していると考えられます。
◆ 解雇の4要件とは
日本の労働契約法では、解雇は「客観的に合理的な理由」があり、「社会通念上相当」と認められなければ無効とされています。さらに、整理解雇であれば「解雇の4要件(人員削減の必要性、回避努力、人選の合理性、手続きの妥当性)」が必要です。
能力不足や素行不良による普通解雇でも、段階的な注意・指導、再配置の検討などを経なければ「合理性あり」とは判断されにくいのが実情です。
◆ 厳しさの正体は、実はメンバーシップ型雇用
日本では、長年にわたって欧米で主流の「ジョブ型雇用」ではなく「メンバーシップ型雇用」が広く採用されてきました。これは、職務内容を厳密に定めず、会社の一員として様々な業務を担当することを前提とした雇用形態です。柔軟な人材活用が可能で、企業の文化やチームワークを重視するという利点も多くあります。
一方で、職務が曖昧であるために、「どのような基準で解雇するか」が明確にしにくく解雇の4要件を満たすのが困難という課題も抱えています。つまり、解雇のしにくさは制度というより、雇用の運用スタイルに由来する部分が大きいのです。
◆ 働き方を見直すことが、対応力を高める鍵に
解雇規制を緩和すべきだという議論もありますが、それ以上に注目されているのが、職務や役割を明確にした雇用運用への見直しです。たとえばジョブスクリプション(職務記述書)を用いて、どの業務をどの水準で担ってもらうかを明確にしておけば、職務不適合が生じた際に、その説明責任や対応がとりやすくなります。
これは「ジョブ型」的なアプローチですが、必ずしも完全にジョブ型へ移行しなければならないというわけではなく、自社の雇用文化に応じた“職務の明確化”を一部取り入れることでも、解雇や人事の透明性は高まります。加えて、日常的な指導・記録、就業規則の整備といった基本的な対応を重ねておくことで、トラブルを防ぎやすくなります。
◆ まとめ
「日本の解雇規制は厳しい」という印象の背景には、法制度よりも雇用のあり方が深く関係しています。
メンバーシップ型にも多くの利点がある一方で、人事処遇の透明性を高める工夫も求められる時代です。制度に頼るのではなく、働き方と運用の見直しによって、解雇をめぐるトラブルを防ぎ、納得感ある対応を可能にすることが、これからの経営に求められる姿勢ではないでしょうか。
2025.5.6
甘夏ニキ