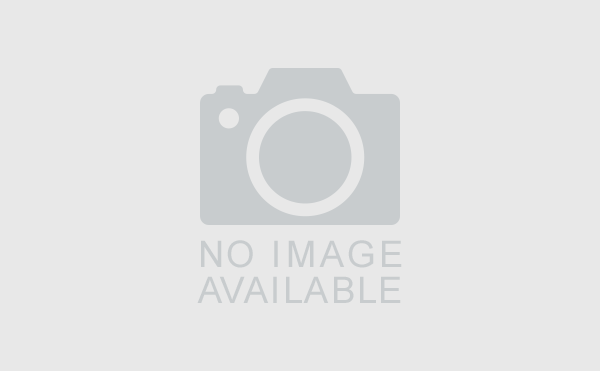すり合わせ国家の逆襲、人型ロボット産業と日中戦略の行方
◆ 日本から中国へ移った人型ロボットの主役
日本はかつて、人型ロボット技術の先端を走っていました。ASIMOやHRPシリーズは世界を驚かせ、「技術立国・日本」の象徴でした。しかし、今やその主役は中国へ移りつつあります。Fourier IntelligenceやUnitree Roboticsは、安価で高機能なヒューマノイドを次々と発表し、量産体制を構築しています。日本が技術的に先行していたにもかかわらず、商用化と社会実装で後れを取った理由は、戦略設計の欠如と、日本独自の「すり合わせ技術」を活かしきれなかった点にあります。
◆ 中国の量産戦略と国家主導の産業構造
中国は「まず動くものを出す」戦略を採用し、完璧を求めるよりも実用性を優先しています。物流・警備・案内など用途を明確化し、モジュール化設計によって部品の精度差をAI制御で吸収することで生産スピードを加速。さらに、国家が補助金と市場インフラを整備し、産業全体を押し上げています。スピードと量を優先するこのアプローチはすでに成果を上げており、人型ロボット産業を次世代製造業として確立しつつあります。
◆ すり合わせ技術の重要性と日本の強み
日本が得意とする「すり合わせ技術」は、異なる部品やシステムを高精度に連携させ、全体の動作や性能を最適化する設計思想です。力・熱・振動・ノイズといった要素を調和させることで、単なる部品の集合ではなく、統合的な技術を実現します。特に人型ロボットのように、モーター・減速機・センサー・皮膚・制御ソフトが複雑に連動する製品では、この技術が不可欠です。つまり、日本は人型ロボット産業において独自の強みを持っています。
◆ 日本の課題:技術はあるが、戦略と出口が不足
日本には世界トップの部品技術がありますが、それを社会に届けるための設計思想、用途開拓、量産体制、国家支援が欠如していました。ロボット関連の政策は省庁間で分断され、研究開発偏重になり、市場との接続が弱かったのです。その結果、すり合わせ技術は“職人芸”として現場に留まり、標準化や量産化が進みませんでした。
◆ 再起に向けたグランドデザイン
それでも、日本には再起のチャンスがあります。減速機・モーター・センサーなどの部品群では世界トップの競争力を維持しており、これを活かすことで産業全体を立て直すことが可能です。人型ロボットは単なる機械ではなく、「人と共に生きる技術」であり、日本独自のすり合わせ技術を活かした産業モデルの確立が求められています。今こそ、国家としてグランドデザインを描き、未来の暮らしと産業の形を世界に提示するべきなのです。
2025.4.23
甘夏ニキ