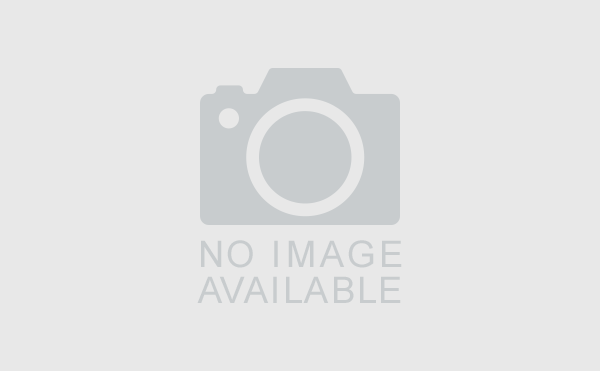オープンイノベーションに飛びつく前に、経営者が考えるべき本質的な問い
◆ オープンイノベーションとは何か
近年、「オープンイノベーション」という言葉を耳にする機会が増えました。
他社や大学、スタートアップなど外部の組織と連携し、知見や技術を共有しながら新たな価値を生み出すという考え方です。
DXやスタートアップ支援、産学連携の文脈でも多く活用されており、特に中小企業にとってはリソース不足を補う手段として注目されています。
しかし、こうした流れに対して、私は一つの疑問を抱いています。
◆ 破壊的イノベーションは“協調”からは生まれていない
本質的なイノベーション、特にビジネスモデルを根本から変えるような「破壊的イノベーション」が、オープンイノベーションから生まれた事例はあるでしょうか。
私の知る限り、AppleのiPhone、Amazonのプラットフォーム戦略、Netflixの転換など、歴史的な変革はすべて一社主導で実現されてきました。
協調や連携を前提とした枠組みでは、意思決定が分散し、リーダーシップを発揮しづらくなります。
つまり、協調からは“本質的な変革”は生まれにくいというのが実情です。
◆ 「リソース不足だから外と組む」は本当に正しいか
企業が自社で将来性のある芽を見つけたとき、「自社リソースだけでは難しいから外と組もう」と考えるのは自然な反応です。
しかし、目的の異なる他社と連携した途端、意思のズレや責任の曖昧さが問題になります。
合弁事業や業務提携、産学連携の多くが頓挫してきた背景には、この構造的なリスクがあります。
大切な変革の芽を、こうした曖昧な関係性の中に投げ込むことが、本当に正しいのでしょうか。
◆ 自社で育てる覚悟“変革の芽”を手放さない選択肢
私が申し上げたいのは、オープンイノベーションを否定するのではなく、「何を外に出し、何を自社で育てるか」を見極めることの重要性です。
もしも将来、事業の柱になるかもしれないと確信する芽があるのであれば、リスクを取ってでも自社で育てるという選択肢があるはずです。
イノベーションとは、単なる手法ではなく、覚悟のある集中と意思決定の積み重ねなのです。
2025.5.10
甘夏ニキ