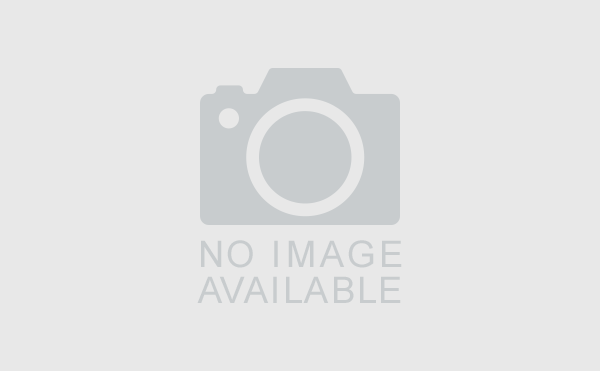知らなかったでは済まされない 中小企業の“解雇リスク”とその回避策
◆ なぜ中小企業では“解雇しやすい”と言われるのか
中小企業では、従業員数が少なく、いわゆる「整理解雇」(経営上の都合による人員整理)という概念はあまり見られません。その代わりに、能力や適性に関する「普通解雇」や、特に多いのは暗黙のうちに辞めてもらう「自己都合退職」が多く見られます。
なぜそうなるかといえば、企業と従業員の距離が近く、日常のコミュニケーションの中で「そろそろ厳しいかな…」という雰囲気が伝わり、本人が退職届を出すようなケースが多いからです。また、労働組合が存在しない、あるいは機能していないこともあり、制度よりも空気感が優先されやすいのです。こうした実情から「中小企業は解雇しやすい」と思われがちですが、そこには見落とされがちな落とし穴があります。
◆ “自己都合退職”の裏に潜む法的リスク
たとえ退職届を提出したとしても、後になって「強要された」「辞めるしかなかった」と主張されると、形式的な自己都合退職も実質的には“解雇”と判断される可能性があります。
実際の労働トラブルでは、「退職を促された」「無言の圧力を感じた」といった曖昧なやり取りが証拠として扱われ、会社側が不利になる事例も少なくありません。
つまり、自主退職のように見せていたとしても、法的にはリスクが消えていないというのが現実なのです。
◆ 中小企業にも求められる「解雇の理解」
労働契約法第16条では、「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効」と明記されています。これは大企業だけでなく中小企業にも適用されます。
さらに、整理解雇では「解雇の4要件」(必要性、回避努力、人選の合理性、手続きの妥当性)が求められますが、普通解雇でも段階的な指導・配置転換の検討・改善の機会提供といったステップを踏むことが重要です。
法制度を知らないまま慣行に頼ることは、後々大きな代償を生むリスクがあるのです。
◆ トラブルを防ぐ“最低限の備え”とは
では、中小企業がとるべき現実的な備えとは何でしょうか。
まず、就業規則を整備し、従業員に周知しておくこと。次に、問題がある従業員には指導内容を記録として残す習慣を持つこと。指導が口頭だけで済まされるケースが多いですが、後で証拠がなければ意味がありません。
さらに、退職面談の際は感情的な言葉を避け、できれば第三者(別の役職者など)を同席させることで、公平性を確保することが重要です。
◆ まとめ
中小企業の現場では、表面上スムーズに処理されているように見える退職でも、実際には“解雇リスク”をはらんでいることがあります。
制度を知らずに現場の慣行だけで対処していると、思わぬトラブルを招くことも。だからこそ、「知らなかった」では済まされないのです。日々の経営の中に、最低限の法的備えと記録文化を根付かせることが、将来の経営リスクを減らす第一歩となるのです。
2025.5.6
甘夏ニキ